「民法は親の同意のない未成年者の契約は取り消せるとする。」
- 京都市の10歳男児がTikTok投げ銭含む約460万円の課金で提訴
- Appleは一部返金も、TikTok運営会社は取材に無回答
- 未成年者契約の取り消しと年齢確認の不備が争点

10歳で280万円の投げ銭…正直、呆れますね。この額はさすがに異常ですよ。
SNSの声
「子供のしたことだから」って逆ギレしてくるパカ親 どこにもいるね
— 疲れた! (@okhotsk285) August 27, 2025
子供のしたことだから許すか払わせるかはサービスを提供している側が決めることだ
これはパスワードも入れないで課金できるスマホを与えたパカ親の責任だ😡
そう出来るよう設定してた親の責任じゃない?何のためのペアレンタルコントロールよ😅😅😅
— 妲己 (@dakki_GB) August 27, 2025
子供はやらかす生き物。
— さて、と。 (@sate_to_x) August 28, 2025
大声で近所に迷惑かけるし、
親のクレカ情報で勝手に購入する。
子供の責任を親に負わす風潮が強まると、「子供を産むリスクは高い」と認識する人がさらに増えるのでは?
子供が店で万引きしたのを店員が注意した件で、
— umesan928 (@umesan928) August 27, 2025
店員に「注意されて子供がトラウマになったらどうするんだ!?」「簡単に取れる場所に置いておくのが悪い!」と逆ギレした親がいたそうですね。
子供が店で万引きしたのを店員が注意した件で、
— umesan928 (@umesan928) August 27, 2025
店員に「注意されて子供がトラウマになったらどうするんだ!?」「簡単に取れる場所に置いておくのが悪い!」と逆ギレした親がいたそうですね。





投稿内容は、あくまで投稿者個人の見解や意見です。
重要な情報については、単一の投稿を鵜呑みにせず、公的機関の発表や複数の報道機関など、異なる情報源からもご確認いただくことが大切です。
考察
今回の騒動、根っこにあるのはやはり「未成年者取消権」という民法の条文ですね。未成年者は判断能力が未熟だからこそ、親の同意がない契約は取り消せる、という考え方は極めて真っ当だと思います。
しかし、問題はここからですよ。今のデジタルサービスにおいて、この「親の同意」をどうやって確認するのか。ソースにもある通り、男児側は「年齢確認の仕組みが不十分」だと主張しています。ユーザーが入力した年齢を鵜呑みにするだけでは、今回のように親のスマートフォンを使った子供が高額課金をしてしまう事態を防げません。
Apple社は一部返金に応じていますが、TikTok運営元のバイトダンス社は「答えられる内容がない」と突っぱねていますね。この対応の違いは、決済システム提供側とサービス提供側の責任の境界線、そして危機管理意識の差を露呈しているように見えます。決済の仕組みとして、例えば一定額以上の課金にはワンタイムパスワードや保護者の承認を必須にするなど、技術的な対策は可能だったはずです。
そして、もちろん保護者の管理責任も問われますが、子供が親のスマホを使うなんて日常茶飯事ですよね。その現実を考えると、プラットフォーム側が「ユーザーの申告」だけに依存するのは、あまりに無責任と言わざるを得ません。今回の提訴は、デジタル時代の「未成年者保護」という、重い課題を突きつけている、そう思いますね。





デジタル時代の未成年者保護、技術と法律、そして企業の倫理が問われますね。
FAQ
- Qこのケースで、なぜ親の同意がないと未成年者の契約は取り消せるのでしょうか?
- A
民法には「未成年者取消権」という規定があり、未成年者が親権者の同意を得ずに結んだ契約は原則として取り消せることになっています。これは、未成年者が十分な判断能力を持たないことを考慮し、彼らを不利益な契約から保護するために設けられた制度なのですね。今回は、まさにその点が法的根拠となっています。
- QAppleは一部返金に応じたのに、TikTok運営元のバイトダンス社が無回答なのはなぜですか?
- A
ソースによると、Apple社は約90万円を返金していますが、バイトダンス社は「答えられる内容がない」と回答を拒否しています。この違いは、決済システム提供者であるAppleと、コンテンツサービス提供者であるTikTok(バイトダンス社)との責任範囲の違い、そして対応ポリシーの差が考えられますね。責任の所在を巡る争いの中で、それぞれが異なるスタンスを取っている、ということだと思います。
- Qこの事件が、今後のオンラインサービスやアプリの年齢確認に与える影響は何でしょうか?
- A
この提訴は、現在の年齢確認の仕組みが不十分であるという問題を明確に突きつけました。今後、オンラインサービスやアプリは、ユーザーの自己申告に依存するだけでなく、より実効性のある年齢確認方法の導入を迫られるでしょう。例えば、保護者の明示的な承認プロセスを組み込んだり、AIを用いた生体認証、あるいは年齢に応じた課金上限設定の義務化など、技術的・制度的な改善が求められることになるはずです。





私が気になったことをQ&Aにしてみました。
気になることがあればコメントをください。
所感
いやもう、正直なところ「10歳で280万円の投げ銭って、どういうことなんだ?」と頭を抱えてしまいますね。今の子供たちは我々の時代とは比較にならないほどデジタルデバイスに触れているのは理解していますが、この金額は尋常じゃない。ゲームのガチャを回す感覚で、投げ銭をしてしまったのかもしれませんが、そのハードルが低すぎる気がします。
「成人であると偽っていても取り消せる」という男児側の主張は、まさにITサービスの「性善説」に一石を投じています。システム側が「ユーザーは正直に年齢を入力するだろう」という前提で作られていたら、こういう問題は必ず起こる。プログラミングのバグと同じで、想定外の入力に対してどう振る舞うか、という設計思想が甘かったと言えるのではないでしょうか。決済フローが簡単すぎる、課金上限の設定が緩いなど、いくらでも改善の余地はあったはずです。
結局のところ、キラキラしたコンテンツでユーザーを集めることに全力を注ぎ、その裏側のリスク管理や社会的責任については後回し、という企業の姿勢が透けて見えますね。本当にこれでいいのか、疑問に思います。





10歳児の280万円投げ銭問題は、デジタル社会の新たな「消費者保護」の形を問いかける提訴です。

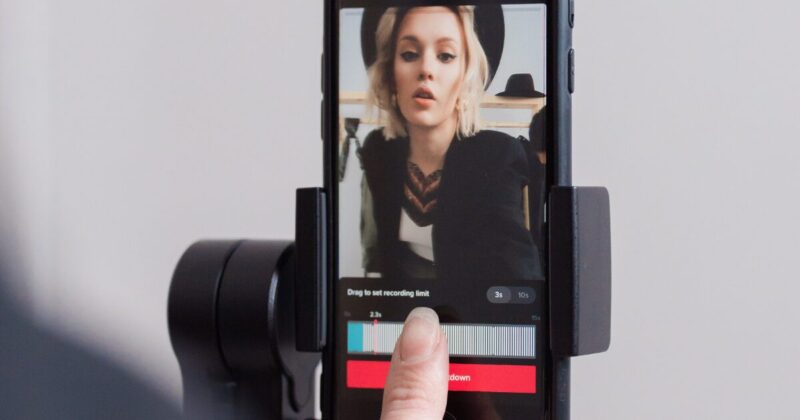


コメント