これまで他行に支払っていた決済手数料を、グループ内で吸収し、その分を顧客へのポイント還元という形で還元できるようになる点
- ドコモは10月1日から住信SBIネット銀行を子会社化し「d NEOBANK」を始動
- 銀行機能と既存サービスを融合させ、dポイント還元などを通じて利便性を高める
- 通信・決済データと金融データを融合し、パーソナルな金融提案を目指す

楽天のこと忘れてない?経済圏、銀行、携帯キャリアの全て持ってますよ。
SNSの声
ドコモが絡む事で不安しか感じない…けどコード決済でメインで使ってるd払いに住信の口座から入金出来なかったがこれが入金出来る様になればちょっと便利か…でもやっぱり不安しか感じない😓
— 酒馬輪燕(しゅばりえ) (@syutter777) September 26, 2025
変わるのが名前だけというのでまあいいか…
— おもぺ氏 ❄️ (@Mr_Mope) September 26, 2025
注意書きだと「現時点では」変更ないとかそういうのばかりなのでとても不安…..
— あいみさき (@shymi_z) September 26, 2025
これが一番ちょうどよい連携。
— ぶたさん2号 (@buta2831191) September 26, 2025
dアカウントを使わせようとか、無駄に「支配」しようとしなくていい。上手くいっているやつをいじる必要は無い。
しいて言うなら、マネックス証券とのマネーブリッジ機能を実装してくれればもう充分。
2000年11月ジャパンネット銀行(PayPay銀行)口座を開設し、同時にイーバンク銀行(楽天銀行)口座を開設し2007年12月に住信SBIネット銀行を開設した。楽天銀行は解約したが2行は現在も取引中。時代の流れを感じます。
— +ipapas (@i_papas) September 26, 2025





投稿内容は、あくまで投稿者個人の見解や意見です。
重要な情報については、単一の投稿を鵜呑みにせず、公的機関の発表や複数の報道機関など、異なる情報源からもご確認いただくことが大切です。
考察
ドコモがこのタイミングで住信SBIネット銀行の子会社化を断行した背景には、日本の巨大IT企業の宿命とも言える「経済圏の維持と拡大」が深く関わっていますね。
ソースからも読み取れる通り、KDDIやソフトバンクが既にグループ内に銀行機能を取り込み、決済サービスと連携させている中で、ドコモは中核となる銀行機能の未提供が長年の課題となっていました。通信事業者が銀行を持つというのは、単なる金融サービスの追加ではなく、顧客の行動を深く把握するための「データの幹線道路」を手に入れる行為なのですね。
銀行が持つ入出金データと、ドコモが持つ通信・決済・ポイント利用データ。この二つが融合すれば、顧客のライフステージ(結婚、住宅購入など)を精確に把握できます。これは、車でいうなら、ただのエンジン性能向上ではなく、AIによる自動運転機能を追加するようなものです。顧客が「今、何を求めているか」を先回りして把握し、「パーソナルな金融商品」を提案する、という極めて効率的かつ強力な収益モデルの基盤が整うわけです。
今回の参入は、単に決済手数料をグループ内で吸収し、ポイント還元を強化する という目先の利益だけでなく、競争が激化する通信業界で顧客を囲い込み、他社に流出させないための、最も重要なインフラ整備だったと言えるでしょう。先行する競合他社に追いつくため、そして巨大経済圏の覇権を争うための、必至の戦略転換だと分析します。





データ融合は次なる収益源だが、プライバシーへの配慮が肝になります。
所感
今回のドコモの銀行参入は、金融サービスがもはや「インフラ」の一部になったことを痛感させられます。昔は銀行というと堅牢で独立した存在でしたが、今はポイント経済圏という巨大な歯車の一部として組み込まれているのですね。
ドコモは「グループ内銀行の強みを生かし、ポイント還元を強化できる」としています。これは聞こえは良いですが、裏を返せば、通信契約やカードの引き落とし先をグループ会社に集約させ、顧客の囲い込みを徹底する、という経営戦略の徹底です。利用者はポイントという甘い餌に惹かれ、深く「ドコモ経済圏」に絡め取られていくわけですね。
しかし、これは競争が激しすぎますから、仕方がないことでしょう。むしろ、KDDIやソフトバンクに遅れを取っていた ドコモが、いよいよ本腰を入れて牙城を築き始めた、という点は評価できます。今後は、ポイントやキャンペーンの華やかさの裏で、どのようにデータが使われ、サービス連携が本当に便利になるのか、その本質的なUX(ユーザー体験)の進化を冷静に見極めていきたいと考えています。





ソースの中で1回も楽天のことは出てきませんでした。

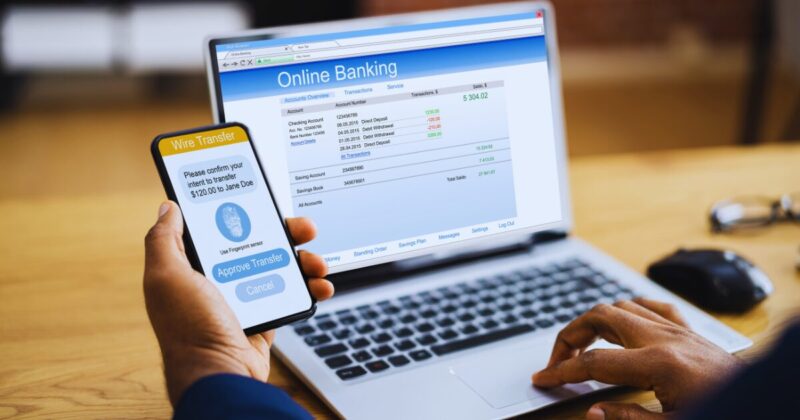


コメント