「有料会員を2万8699件としていましたが、直近でアクセス実績がある有料会員数はわずか2236件に過ぎないと報告されています。」
- AI企業オルツは架空売上や会員水増しで上場後10ヶ月で廃止
- 元CFOが主導し巧妙な粉飾、前任監査法人の指摘も後任が見逃す
- 「応援ムード」が蔓延し、多くの関係者が不正を見抜けず

AIベンチャーの華やかさに隠れた、あまりにも古典的で悪質な手口。現場の感覚と乖離した数字は、やはり危ういですね。
SNSの声





投稿内容は、あくまで投稿者個人の見解や意見です。
重要な情報については、単一の投稿を鵜呑みにせず、公的機関の発表や複数の報道機関など、異なる情報源からもご確認いただくことが大切です。
考察
今回のオルツの不正会計問題、その根本原因はいくつか考えられますね。まず挙げられるのは、創業社長の上場への「強すぎる執着」です。業績が伸び悩む中で、資金繰りのために安易に粉飾に手を染めてしまった。まるで、プロジェクトの納期が迫っているのに、コードの品質を無視して場当たり的な修正を繰り返すようなもので、根本的な解決にはなりません。
そして、その不正を巧妙にしたのが、元外資金融出身のCFOの存在です。彼はIPOやM&Aの経験から、投資家や証券会社がどこを scrutinize するか、つまり「どこを重点的に見るか」を熟知していた。これはまるで、セキュリティの専門家が、システムの脆弱性を悪用する方法を知っているようなもので、悪用されれば非常に厄介ですね。偽造の広告発注書など、手口もかなり周到だったようです。
さらに、本来なら経営の監視役である監査法人が、その役割を果たせなかった点が大きいでしょう。前任の監査法人は循環取引の疑念を指摘し、契約を解消しています。これは健全な判断だと思いますが、後任のシドー監査法人は、その引き継ぎを受けながらも経営陣の虚偽説明を鵜呑みにしてしまった。常勤職員9人の小所帯で、AI業界という専門性の高い分野の監査には力量不足だった可能性も指摘されています。まるで、最新の複雑なサーバー環境を、昔ながらのチェックリストだけで監査しようとしたような状況かもしれません。
そして、ベンチャー企業を取り巻く「応援ムード」も、不正を見逃す温床になったと思われます。上場を目指す企業は、キラキラした夢を語ることが多いですが、地に足がついた数字の裏付けがあるか、冷静に見極める視点が欠けていたのでしょう。これは、流行りの技術に乗っかって、中身のないプロダクトを「すごい」と持ち上げる風潮にも似ていますね。





夢を追うベンチャーを取り巻く「性善説」と、監視体制の穴が悪質な不正を許した。
FAQ
- Qなぜ「AI新興企業」という点が、不正を見抜くことを難しくしたのでしょうか?
- A
AIという先端技術を扱う新興企業は、ビジネスモデルが複雑で、従来の製造業などと異なり「物質的な実体」が少ないため、監査が難しくなりがちです。また、成長への期待感が先行し、技術の詳細や実態を深く検証する視点が疎かになりやすい側面もあったと推測されます。
- Q経営陣が意図的に結託した場合、監査法人ですら見抜けないという意見は妥当だと思いますか?
- A
日本取引所グループのCEOも同様の意見を述べています。確かに、上層部が悪意を持って偽装した場合、外部からの監査は非常に困難になります。しかし、前任の監査法人が循環取引の疑いを指摘したにも関わらず、後任の監査法人が十分な確認を怠った点には、専門家としての責任が問われると考えられます。
- Q「応援ムード」が不正を見逃す温床となった、この問題からベンチャー企業はどう学ぶべきですか?
- A
成長を期待する「応援ムード」は企業の原動力ですが、性善説に頼りすぎると内部の不正を見過ごすリスクを高めます。ベンチャー企業は、外部からの期待に応えつつも、常に自社のガバナンス体制を強化し、客観的な視点で事業実態を透明化する努力が不可欠です。信頼は一度失うと取り戻すのが非常に難しいものですね。





私が気になったことをQ&Aにしてみました。
気になることがあればコメントをください。
所感
今回の件は、IT業界に身を置く私にとっても非常に残念なニュースです。AIという未来を切り拓く技術を扱う企業が、こんなにも古典的で悪質な粉飾に手を染めていたとは、呆れてしまいますね。まるで、最新鋭のAIを搭載した自動運転車が、実はハンドルを切るのが人間だった、というような話です。
特に気になったのは、監査法人やVC、東証までもが「だまされた」と発言していることです。確かに経営層が結託すれば見抜くのは難しいかもしれませんが、プロフェッショナルとして、もう少し踏み込んだ確認ができなかったのか、と疑問に感じますね。もし私がこの会社のシステム担当者だったら、売り上げの数字が本当に実体に基づいているか、ログデータやアクセス状況、顧客とのやり取りなど、技術的な側面からも確認を試みるでしょう。
AI GIJIROKUの契約アカウントの実在性を確認しなかったというのは、現代のITサービスにおいて、システムのログを見ればすぐに分かることではないかと思うのですよ。データに基づいた証拠確認が、もっと徹底されるべきだったと感じます。
新興企業を「応援したい」という気持ちは分かりますが、それが性善説に傾きすぎて、批判的な視点や冷静な検証を欠いてしまうのは非常に危険ですね。キラキラしたプレゼンに騙されず、数字の裏にある「本物」を見極める力が、私たちITエンジニアにも、そして投資家や関係機関にも、今こそ求められていると思います。





AI新興企業の不正会計は、監視体制の甘さと「応援ムード」が生んだ悲劇。

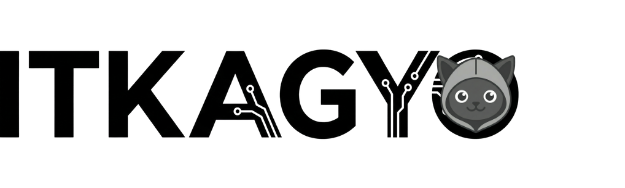



コメント