- アドフラウドは企業のネット広告費を狙う詐欺で、世界で年約12兆円の被害
- ボットや生成AIで偽クリックや低品質サイトを量産し、広告収益をだまし取る巧妙な手口
- 仕組みの複雑さや摘発の難しさ、経営層の理解不足が対策を阻む要因

あなたが担当している広告のCPAが合わないのはこのせいかも?
SNSの声
ネット社会だから起きた弊害
— CRおばけらどん👻 (@CR_ZENZENDEN) August 16, 2025
悪いことを考える人は本当に天才集団だよな…
それらのことを真っ当な事に費やせば世界は良くなる…
そんなお花畑は…資本主義にはこない
狙われる企業のネット広告費◆世界で被害12兆円の詐欺「アドフラウド」とは(時事通信)
https://t.co/uYdYSSl5Dk
「アドフラウド」や「質のいい広告掲載面」の議論は10年以上前から行われてきたが、今こうして記事になるのは一般的にはまだまだ知られていない証。広告主への啓蒙を僕らも続けていかないといけない
— Kazuma Hattori | デジタル広告・マーケの人 (@KazumaHattori) August 18, 2025
狙われる企業のネット広告費◆世界で被害12兆円の詐欺「アドフラウド」とはhttps://t.co/FGZ5tI4oAU
アドフラウド
— 明るく生きる!!あーちゃん (@happy_archan) August 17, 2025
ネット広告であたかも閲覧したように見せかけ広告主から広告費をだまし取るアドフラウドという手法の被害が増大しているそうです
生成AIを利用し手口が巧妙化しているそうです
広告は大事なPRであり費用も掛かる為広告主もよく精査して出したいですね#アドフラウド





ただでさえGoogle、Metaに日本から広告費が流れてるのに、不正でも海外にお金が流れてるようです。
考察
アドフラウドが世界的に拡大し、対策が困難になっている背景には複数の要因が複合的に絡み合っていると考えられます。
まず、インターネット広告費の急増が挙げられます。電通の発表によると、2024年のネット広告費は過去最高の3.6兆円に達し、広告費全体の約半分を占めるに至りました。ネット利用者の増加や、広告単価の安さ、幅広い層への配信の利便性がこの拡大を後押ししています。しかし、このように巨額の資金が流れ込む場所には、必然的に犯罪の手が伸びやすくなります。
次に、手口の巧妙化と多様化が挙げられます。特に、自動で大量の偽クリックを行う「ボット」の悪用や、生成AIを用いて広告収益目的の低品質なサイトを大量生産する手口が顕著です。これらの技術の進歩は、より効率的かつ大規模な詐欺を可能にし、従来の対策をすり抜ける原因となっています。
さらに、ネット広告の取引構造の複雑さも大きな要因です。広告主と広告掲載サイトの間には、多数の広告代理店やプラットフォーム事業者が介在し、自動的に大量の広告が取引されています。この複雑な多層構造のせいで、どの段階で詐欺行為が発生したのかを特定・立証することが極めて困難です。容疑者が海外にいたり、ドメインやアカウントを頻繁に変更したりすることも、追跡をより一層困難にしています。
加えて、法的措置の困難性があります。松原諒弁護士は、詐欺としての取り締まりが非常に難しいと指摘しており、民事上の損害賠償請求も、個々の被害額が限定的であることや因果関係の立証が難しいことから、費用に見合わない恐れがあるとしています。これにより、アドフラウドは「稼ぎやすく、捕まりにくく、生成AIを使って簡単に実行できる『低リスクの犯罪』」という認識が生まれてしまっています。
最後に、広告主側の経営層の理解不足と「クリック至上主義」が、対策の遅れを招いています。現場の広告担当者がリスクを認識していても、「パフォーマンスを上げろ」という経営層からの要求や、対策にかかる負担への抵抗感から、対策を徹底できない実態があるようです。短期的な成果としてのクリック数を過度に重視する姿勢が、広告の「質」を見落とす結果となり、不適切なサイトへの掲載を許容してしまうことにも繋がっています。また、広告代理店任せの姿勢や、自治体のような公的機関の対策の遅れも課題として指摘されており、業界全体の意識改革と連携が急務であると言えるでしょう。
FAQ
- Qアドフラウドとは何ですか?
- A
アドフラウドとは、botなどのプログラムや悪意のある第三者が広告の表示回数やクリック数を不正に水増しし、広告費をだまし取る広告詐欺のことです。
実際にはユーザーに届いていない広告に対して、広告主は無駄な費用を支払わされることになります。デジタル広告市場の拡大に伴い、その被害は深刻化しています。
アドフラウドの主な手口
アドフラウドには様々な手口が存在しますが、代表的なものは以下の通りです。
| 手口の種類 | 内容 |
|---|---|
| ボット・クリックファーム | 自動化されたプログラム(ボット)や、低賃金で雇われた人々(クリックファーム)が、機械的または手動で大量の広告クリックやインプレッションを発生させます。 |
| 隠し広告 (アドスタッキング) | ユーザーには見えないように、複数の広告を重ねて表示したり、1×1ピクセルのような極小サイズで表示したりして、表示回数だけを不正に稼ぎます。 |
| ドメイン・スプーフィング | 価値の低いサイトや不適切なサイトを、信頼性の高い優良サイトであるかのように偽装し、高値で広告を配信させます。 |
| 広告インジェクション | ユーザーのブラウザにマルウェアなどを介して、本来広告が表示されないウェブサイトに強制的に広告を表示させたり、既存の広告を別のものにすり替えたりします。 |
| クッキー・スタッフィング | ユーザーが訪問していないサイトのクッキーをブラウザに不正に付与します。その後、そのユーザーが別の経路で商品購入などの成果に至った際に、あたかも自分の広告の成果であるかのように見せかけ、不正に報酬を得ます。 |
- Qアドフラウドで逮捕された事例はありますか?
- A
残念ながら、日本国内において「アドフラウド」という罪名で直接的に逮捕されたという公式な事例は、現時点では確認されていません。
しかし海外では、アドフラウドで大規模な逮捕劇に発展したケースも存在します。例えば、「Methbot」と呼ばれる大規模なアドフラウドのオペレーションに関わった人物が逮捕・起訴され、有罪判決を受けています。これは、数百万ドル規模の被害を出した大規模な広告詐欺事件でした。
結論として、日本ではまだ「アドフラウド」での逮捕事例はありませんが、水面下では多くの被害が発生していると考えられます。今後、法整備や捜査技術の進展によって、日本でも摘発されるケースが出てくる可能性は十分にあります。





他にも気になることがあればコメントをください。
所感
今回の「アドフラウド」に関する記事を拝読し、その被害規模の甚大さに改めて驚きました。世界で年間12兆円という金額は、想像を絶する規模であり、これが企業の広告費から不正に流出し、さらには違法サイトの資金源になっているという事実は、看過できない社会問題だと感じました。
特に印象的だったのは、この詐欺が「低リスクの犯罪」と表現されている点です。生成AIなどの最新技術を悪用し、複雑な広告エコシステムの隙間を縫って行われるため、摘発が極めて難しいという現状は、まさに現代社会の闇を象徴しているように思えました。企業が被害者でありながら、意図せずして不適切な活動を助長してしまうという構造は、デジタル化が進む社会における新たな倫理的課題を突きつけているようにも感じられます。
また、対策が進まない原因として、広告主側の経営層の理解不足が挙げられていることにも、深く共感いたしました。現場がリスクを認識しても、短期的な成果や費用対効果を優先するあまり、本質的な対策が後回しにされてしまうという構図は、多くの企業で見られる課題ではないでしょうか。「クリック至上主義」への疑問提起や、「広告は社会の鏡」という言葉は、私たち利用者側も単に「うっとうしい」と感じるだけでなく、その背景にある問題に関心を持つべきだという示唆を与えてくれます。
インターネット空間を安全で信頼できるものにするためには、単一の企業や組織の努力だけでは限界があり、まさに「業界全体」での取り組みが不可欠であると痛感いたしました。今回の取材が、この問題への意識を高める一助となることを願ってやみません。





ここまで被害額が大きいとアドフラウドは、不況の要因の1つになってると思います。

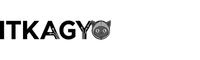



コメント