ざっくりとフェイルオーバーとは
- 故障時の自動切り替え
- ホットスタンバイの一部
- 予備システムの活用

フェイルオーバーとは、故障時の自動切り替えです。
概要説明
フェイルオーバーとは、システムやネットワークが故障した際の自動切り替えである。 なぜならば、主要システムのダウンタイムを最小限に抑えるため。
例えば、オンラインショップである。そして、売上損失を防ぐため。つまり、ビジネス継続性を保つためである。だから、多くの企業で導入される。
職業職種
システムエンジニア
システムエンジニアは、フェイルオーバーを利用する。なぜなら、システムの継続性を保つため。例えば、企業の基幹システム。
ネットワークエンジニア
ネットワークエンジニアは、フェイルオーバーを導入する。なぜなら、ネットワークの断線や故障から迅速に回復するため。例えば、データセンターのネットワーク。
ITマネージャー
ITマネージャーは、フェイルオーバーの導入を決定する。なぜなら、ビジネスの安定性と継続性を保つため。例えば、クリティカルな業務アプリケーション。

フェイルオーバーは、名前の由来は英語の”Fail”(失敗する、故障する)と”Over”(乗り越える、超える)です。
フェイルオーバーの手順例
以下は、フェイルオーバー実行の基本手順です。システムの監視
システムの状態を常にチェックする。なぜなら、故障の前兆を早く察知できるから。例えば、異常な動作や速度の低下。
ホットスタンバイの確認
予備となる機器やシステムが正常に動作しているかを確認する。なぜなら、故障時にすぐに切り替える必要があるから。例えば、予備の電源や接続状態の確認。
自動切り替えの設定
主のシステムが故障した時に、自動で予備に切り替わるよう設定する。なぜなら、人が介入しなくても迅速に切り替えることができるから。例えば、故障検知後の自動切り替えの設定。
故障発生時の対応
故障が発生した場合、ホットスタンバイに切り替える。なぜなら、サービスの中断を最小限にするため。例えば、ネットワークの再接続やデータの同期。
故障原因の分析
切り替えが完了した後、故障の原因を調査する。なぜなら、同じ故障を防ぐための対策を立てる必要があるから。例えば、故障部分のログ分析や設定の確認。
類似語
ホットスタンバイ
ホットスタンバイは、主の機器やシステムの予備として待機している状態である。なぜなら、すぐに切り替えが必要な時に備えているから。例えば、データセンターでのバックアップ機器。
スイッチオーバー
スイッチオーバーは、手動でシステムや機器の切り替えを行うことである。なぜなら、自動切り替えができない場合や特定のタイミングで切り替えたい時に使われるから。例えば、メンテナンス時の切り替え。
冗長化
冗長化は、システムや機器のバックアップを持つことである。なぜなら、一つの部分が故障しても他の部分で代替することができるから。例えば、サーバーやネットワークの複数の経路。
反対語
フェイルバック
フェイルバックは、予備のシステムから主のシステムへの切り替えである。なぜなら、フェイルオーバー後、主のシステムが復旧したときに元の状態に戻すためだ。例えば、故障したサーバーが修復された後。
復旧
復旧は、故障や問題から正常な状態に戻す行為である。なぜなら、システムやサービスの継続的な稼働を確保するためだ。例えば、データベースのデータ復旧。
スイッチバック
スイッチバックは、代替の手段から元の方法やルートに戻ることである。なぜなら、元の方法やルートが再び使用可能になったからだ。例えば、通信路の切り替え。
フェイルオーバーの注意点
フェイルオーバーを使用する時の注意点は設定の正確さである。なぜならば間違った設定では適切に切り替えが行われないからだ。
例えば、ネットワークのアドレス設定ミスである。そして、予備のシステムの状態も定期的に確認することが必要だ。だから、テストや継続的な監視が大切だ。

フェイルオーバーとスイッチオーバーは、間違えやすいので注意しましょう。
フェイルオーバーは、主のシステムがダウンしたときに予備のシステムに自動で切り替わることです。

一方、スイッチオーバーは、手動での切り替えを指す。
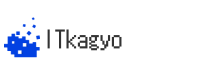
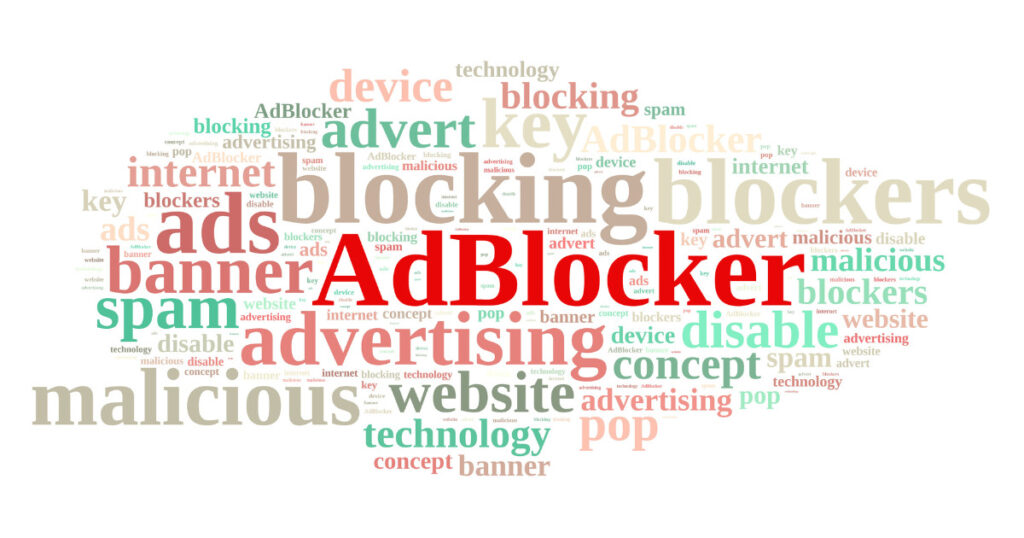

コメント