ざっくりとマン・イン・ザ・ブラウザ攻撃とは
- ブラウザ内での攻撃
- 個人情報の盗難
- リアルタイムで操作

マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃とは、ブラウザ内で情報を盗む攻撃です。
概要説明
マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃とは、ユーザーのウェブブラウザ内で行われる攻撃である。なぜならば、この攻撃はマルウェアによってブラウザが侵害され、ユーザーが入力した情報(例えば、パスワードやクレジットカード情報)を盗むからである。
例えば、オンラインバンキングのセッション中に行われる。そして、攻撃者はリアルタイムでユーザーの操作を盗み、改ざんすることができる。
つまり、ユーザー自身が攻撃に気づかないまま情報が盗まれるのである。だから、高度なセキュリティ対策が必要である。
職業職種
サイバー犯罪者
サイバー犯罪者は、金銭的利益を得るためにこの攻撃を使用する。なぜなら、個人の銀行情報やクレジットカード情報を盗むことができるから。例えば、オンラインバンキングの情報を盗む。
ハッカー
ハッカーは、技術的な挑戦としてこの攻撃を行うことがある。なぜなら、セキュリティシステムを突破し、自身の技術を証明したいから。例えば、大企業の内部情報を盗む。
スパイ
スパイは、政府や企業の機密情報を盗む目的でこの攻撃を使用する。なぜなら、デジタル情報が今の時代の重要な情報源であるから。例えば、国家間の機密情報を盗む。

マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃は、名前の由来は「マン・イン・ザ・ミドル攻撃」から派生しています。この攻撃は、通常の「マン・イン・ザ・ミドル攻撃」がネットワークの中間で行われるのに対し、ブラウザ内で行われるため、「ブラウザ」が名前に含まれています。
マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃の代表例
Zeus
Zeusは、マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃で有名である。なぜなら、このマルウェアはオンラインバンキング情報を盗むために設計されているから。例えば、ユーザーのキーストロークを記録する。
SpyEye
SpyEyeは、マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃で名高い存在である。なぜなら、Zeusと同様にオンラインバンキングの情報を盗むことができ、その後Zeusを上回る機能を持つようになったから。例えば、セキュリティソフトを無効化する機能。
Gozi
Goziは、マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃で世間に知られている。なぜなら、このマルウェアは世界中の銀行を狙い、数百万ドルもの金額を盗んだから。例えば、米国の主要な銀行を狙った攻撃。
手順例
以下は、マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃の実行手順です。マルウェアの作成
マルウェアを作成する。なぜなら、このマルウェアがユーザーのブラウザに侵入し、情報を盗むための基盤となるから。例えば、キーロガーやスクリーンショットの機能を持つ。
配布手段の選定
マルウェアをユーザーのコンピュータに配布する手段を選定する。なぜなら、マルウェアを効果的に広める方法を考えなければならないから。例えば、フィッシングメールや偽のウェブサイト。
情報の収集
マルウェアがユーザーのブラウザに侵入した後、情報を収集する。なぜなら、この情報が攻撃者の目的を達成するための重要なデータであるから。例えば、ログイン情報やクレジットカード情報。
情報の送信
収集した情報を攻撃者のサーバに送信する。なぜなら、攻撃者はこの情報を使って不正な行為を行うから。例えば、銀行口座からの不正な送金。
痕跡の消去
攻撃が完了した後、痕跡を消去する。なぜなら、攻撃者は自身の正体を隠すために、証拠を消し去る必要があるから。例えば、マルウェアの自動削除。

マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃を実行してはいけません。
類似語
Phishing
Phishingは、マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃の類似語である。なぜなら、両者ともにユーザーから情報を盗む目的で行われる攻撃であるから。例えば、偽のウェブサイトを使ってユーザーの情報を盗む。
Keylogging
Keyloggingは、マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃の類似語である。なぜなら、両者ともにユーザーのキーストロークを記録し、情報を盗む手法を使用するから。例えば、パスワードやクレジットカード情報の盗難。
Session Hijacking
Session Hijackingは、マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃の類似語である。なぜなら、両者ともにユーザーのセッションを乗っ取り、不正な行為を行う攻撃であるから。例えば、ログイン済みのアカウントを乗っ取って情報を盗む。
反対語
セキュアブラウジング
セキュアブラウジングは、マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃の反対語である。なぜなら、ユーザーのブラウジングを安全に保護する行為であるから。例えば、HTTPSの使用。
データ保護
データ保護は、マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃の反対語である。なぜなら、ユーザーのデータを盗むのではなく、保護する行為であるから。例えば、暗号化技術の使用。
認証強化
認証強化は、マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃の反対語である。なぜなら、不正なアクセスを防ぐためのセキュリティ強化の手段であるから。例えば、二要素認証。
マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃の注意点
マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃を使用する時の注意点は、法的なリスクである。なぜならば、この攻撃は違法な行為であり、逮捕や訴訟の対象となる可能性があるからだ。
例えば、個人情報の盗難である。そして、社会的な信用を失う可能性もある。だから、絶対に行わないように。

マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃とマン・イン・ザ・ミドル攻撃は、間違えやすいので注意しましょう。
マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃は、ブラウザに侵入してユーザーの情報を盗む攻撃です。

一方、マン・イン・ザ・ミドル攻撃は、通信の途中で情報を盗む攻撃です。
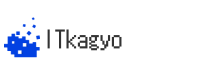
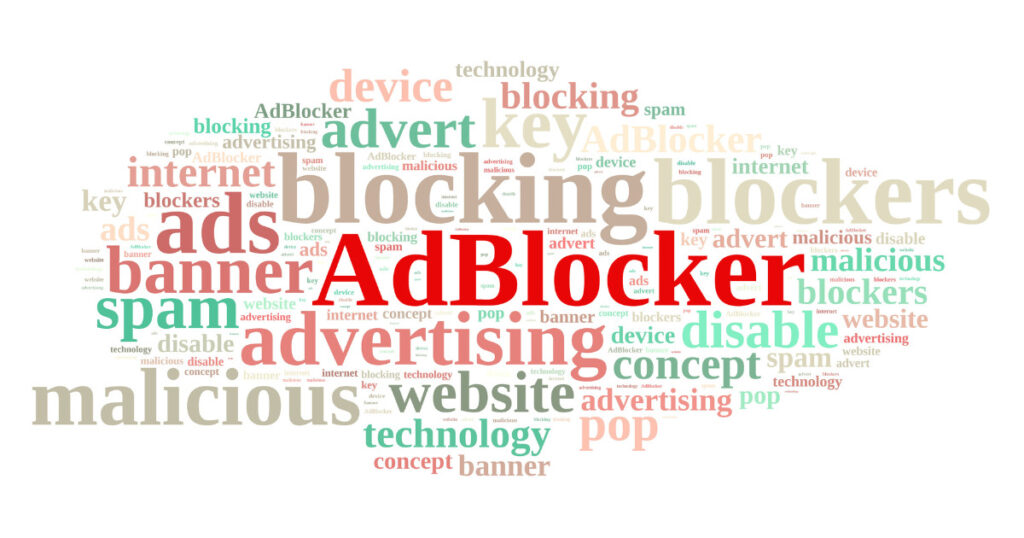

コメント