- クラウド経由でソフトウェアを利用する形態
- インストールや管理は不要
- 月額や利用量に応じた支払い

もっとくわしく知りたい人は続きをどうぞ!
SaaSをわかりやすく
SaaSとは
- クラウド経由でソフトウェアを利用する形態: ソフトウェアを自身のコンピューターにインストールするのではなく、インターネットを通じてサービスとして利用する形態を指す。これは、従来のソフトウェアの利用方法とは大きく異なる点。インターネット環境があれば、場所やデバイスを問わず、必要な時に必要なソフトウェアを利用できるため、利便性が高い。この手軽さが、SaaSが多くのユーザーに支持される理由の一つ。
- インストールや管理は不要: SaaSの利用者は、ソフトウェアのインストール作業や、それに伴うアップデート、保守管理などを一切行う必要がない。これらの作業はすべて、SaaSを提供する事業者(プロバイダー)によって行われる。利用者は、常に最新の状態のソフトウェアを手間なく利用できる。これは、特にITに詳しくない初心者にとって大きなメリットとなる。
- 月額や利用量に応じた支払い: SaaSの料金体系は、一般的に月額または年額の定額制や、利用した量に応じて料金が発生する従量課金制が採用されている。これにより、初期費用を抑え、必要な機能や利用規模に応じて柔軟にコストを調整できる。特に、事業規模が変動しやすいスタートアップや中小企業にとって、この柔軟性は大きな魅力となる。
SaaSの目的と基本的な概念
SaaSの主な目的は、これまで高価であったり、自社で運用するには専門知識が必要であったりした高性能なソフトウェアを、より多くの人々や企業が手軽に利用できるようにすること。また、ソフトウェアの管理やメンテナンスの煩雑さから解放し、利用者が本来の業務に集中できる環境を提供することも目指している。
SaaSの基本的な概念は、「クラウドコンピューティング」という技術に基づいている。これは、インターネットを通じて、ソフトウェアやデータなどのITリソースを利用する考え方。SaaSプロバイダーは、自社のサーバーやデータセンター、あるいは第三者のクラウドプラットフォーム上にソフトウェアとデータを保管し、利用者はインターネット経由でそれらにアクセスする。従来のソフトウェアが製品として購入され、個々のコンピューターにインストールされていたのに対し、SaaSはサービスとして提供され、利用者は必要な期間だけ利用権を借りるようなイメージである 。多くの場合、SaaSアプリケーションはWebブラウザを通じて利用できるため、特別なソフトウェアをインストールする必要がない
SaaSの効率性を支える重要な技術要素の一つに、「マルチテナントアーキテクチャ」がある。これは、一つのソフトウェアの仕組み(インスタンス)を複数の顧客(テナント)が共有する方式。各顧客のデータは分離され、安全に管理されるため、他の顧客のデータが混ざる心配はない。このアーキテクチャにより、SaaSプロバイダーはインフラや運用コストを効率化でき、その結果、利用者は低価格で高品質なサービスを利用できる
SaaSとは わかりやすい例
日常的な例
多くの人が日常的に利用しているサービスの中にも、SaaSモデルで提供されているものが数多く存在する。例えば、GmailやYahoo! MailなどのWebメールサービスは、インターネットを通じてメールの送受信を行うため、SaaSの一種と言える。また、GoogleカレンダーやiCloudカレンダーなどのカレンダーツールも、クラウド上でデータが管理され、複数のデバイスからアクセスできるためSaaSに該当する。
ビジネスの現場では、Microsoft Office 365やGoogle Workspace(旧G Suite)といったオフィスツールが広く利用されている。これらのサービスは、文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの機能がクラウド上で提供され、ユーザーはサブスクリプション契約に基づいて利用する。
さらに、Facebook、X(旧Twitter)、Instagramなどのソーシャルメディアプラットフォームも、ユーザーがインターネットを通じてコンテンツを共有し、コミュニケーションを取るサービスであり、SaaSの代表的な例。音楽配信サービスのSpotifyや動画配信サービスのNetflixといったエンターテイメントサービスも、クラウド上にコンテンツが保存され、ユーザーは好きな時にストリーミング再生できるため、SaaSとして捉えることができる。
ビジネスの例
IT分野では、SaaSは多岐にわたる業務で活用されている。顧客関係管理(CRM)ソフトウェアのSalesforceは、営業活動や顧客管理を効率化するためのSaaSとして多くの企業で採用されている。企業資源計画(ERP)システムも、NetSuiteなどのクラウドベースのソリューションが登場し、SaaSとして利用されるケースが増えている。
会計ソフトウェアのQuickBooksやXeroは、経理業務を自動化し、財務状況を可視化するのに役立つSaaS。人事(HR)ソフトウェアも、従業員の管理や給与計算などを効率化するSaaSとして、多くの企業で導入が進んでいる。プロジェクトの進捗管理やチーム内のコミュニケーションを円滑にするプロジェクト管理ツールのTrelloやAsana、ConfluenceなどもSaaSとして提供されている。
その他にも、メールマーケティングソフトウェア、セキュリティソフトウェア、コラボレーションツール(Slack、Zoom、Microsoft Teams)、ドキュメント編集サービスなど、様々な種類のソフトウェアがSaaSとして提供されており、企業の規模や業種を問わず、幅広いニーズに対応している。
主要なSaaSアプリケーションの例
| SaaSアプリケーションの種類 | 具体的な例 |
|---|---|
| メール | Gmail、Outlook.com、Yahoo! Mail |
| オフィススイート | Microsoft 365、Google Workspace |
| CRM (Customer Relationship Management) | Salesforce、HubSpot CRM |
| ERP (Enterprise Resource Planning) | NetSuite,、SAP S/4HANA |
| プロジェクト管理 | Trello、Asana、Jira |
| コミュニケーション | Slack、Microsoft Teams、Zoom |
| 会計 | QuickBooks、Xero、Freee会計 |
| 人事 | BambooHR、Workday |
SaaSを使用する手順
- 1インターネット接続とデバイスの準備
SaaSアプリケーションを利用するためには、インターネットに接続できる環境と、コンピューター、スマートフォン、タブレットなどの対応デバイスが必要となる。
- 2SaaSアプリケーションへのアクセス
利用したいSaaSアプリケーションのWebサイトをWebブラウザで開くか、専用のモバイルアプリやデスクトップアプリを起動する。
- 3アカウント登録 (初回のみ)
初めて利用する場合は、通常、アカウント登録が必要となる。Webサイトやアプリの指示に従い、氏名、メールアドレスなどの情報を入力し、パスワードを設定する。
- 4ログイン
登録が完了したら、登録したメールアドレスまたはユーザー名とパスワードを入力してログインする。既にアカウントを持っている場合は、この手順から開始する。
- 5ソフトウェアの利用
ログインが完了すると、SaaSアプリケーションの機能を利用できるようになる。文書作成、データ分析、顧客管理など、ソフトウェアによって様々な機能が提供されている。
- 6データの保存
SaaSアプリケーションで作成したり、編集したりしたデータは、通常、自動的にクラウド上に保存される。これにより、どのデバイスからでも最新のデータにアクセスできる。
- 7ログアウト (必要に応じて)
利用が終わったら、セキュリティのためにログアウトすることが推奨される。特に、共有のデバイスを利用している場合は、必ずログアウトするように心がける。
SaaSアプリケーションの利用は、このように簡単な手順で開始できる。背後では、SaaSプロバイダーがインフラの管理、セキュリティ対策、ソフトウェアのアップデートなどをすべて行っているため、利用者はこれらの複雑な作業を意識する必要がない。この手軽さが、SaaSの大きな魅力の一つ。
SaaSについてのよくある質問
- QSaaSとは何ですか?
- A
ソフトウェアをインターネット経由で利用するサービスです。インストールや管理は不要で、月額や利用量に応じて料金を支払います。
- QSaaSのメリットは何ですか?
- A
低コストで始められ、どこからでもアクセス可能で、自動的にアップデートされます。また、必要に応じて利用規模を拡大・縮小できます。
- QSaaSのデメリットは何ですか?
- A
インターネット接続が必要で、カスタマイズの自由度が低い場合があります。また、セキュリティやデータの管理をプロバイダーに依存する部分があります。
- QSaaSの例を教えて下さい。
- A
GmailやGoogleドキュメント、Salesforce、Zoomなどが挙げられます。
- QSaaSは安全ですか?
- A
多くのSaaSプロバイダーはセキュリティ対策に力を入れていますが、利用する側も適切な対策を講じる必要があります。
- Q従来のソフトウェアとどう違うのですか?
- A
従来のソフトウェアは購入して自分のコンピューターにインストールしますが、SaaSはインターネット経由で利用し、インストールや管理は不要です。
- QSaaSの料金体系はどうなっていますか?
- A
一般的には月額または年額のサブスクリプションモデルや、利用量に応じた従量課金モデルがあります。
- QSaaSを利用するために必要なものは何ですか?
- A
インターネットに接続されたデバイス(コンピューター、スマートフォン、タブレットなど)と、Webブラウザがあれば利用できます。
SaaSの背景や歴史
SaaSの概念は、比較的最近登場したものではなく、その起源は1960年代にまで遡ることができる
初期の概念 (1960年代~1990年代):
1960年代には、タイムシェアリングという考え方が登場した。これは、一台の大型コンピューターを複数のユーザーが共有して利用する方式であり、SaaSの原型とも言える。当時はコンピューターが高価で、一部の大企業や研究機関しか所有していなかったため、複数のユーザーで共有することで、より多くの人がコンピューターの恩恵を受けられるように考えられた。1980年代には、企業はメインフレームやミニコンピューターを利用して、社内でソフトウェアアプリケーションを実行していた。この頃から、ソフトウェアをサービスとして提供する動きも見られたが、多くは社内ネットワークに限られていた。1990年代に入ると、インターネットが徐々に普及し始め、初期のWebアプリケーションが登場した。これにより、インターネットを通じてソフトウェアを利用するというアイデアが現実味を帯びてきた。
SaaSの登場と普及 (1990年代後半~2000年代):
現代のSaaSの始まりとして広く認識されているのは、1999年に設立されたSalesforceの登場。Salesforceは、顧客関係管理(CRM)ソフトウェアをクラウドベースで提供し、従来の買い切り型のソフトウェアライセンスではなく、月額課金制という新しいビジネスモデルを導入した。2000年代に入ると、インターネットの普及がさらに進み、ハードウェアやソフトウェアのコストが低下したこともSaaSの普及を後押しした。より高度な機能を持つSaaSアプリケーションが登場し始め、企業は自社でインフラを構築・管理することなく、必要なソフトウェアを利用できるようになった。2004年にはGmail、2006年にはAmazon Web Services (AWS)、2007年にはOffice 365が登場し、SaaSの利便性や可能性を広く示すことになった 。特にAWSの登場は、SaaSプロバイダーにとってインフラの構築コストを大幅に削減する機会を提供し、SaaS市場の成長を大きく加速させた。
現在の状況 (2010年代~現在):
2010年代に入ると、SaaSはソフトウェアの提供モデルとして主流となり、あらゆる規模の企業がクラウドベースのソフトウェアを利用するようになった 。柔軟性や拡張性の高さ、コスト効率の良さなどが評価され、SaaSの需要は急速に拡大した。2020年以降は、COVID-19パンデミックの影響により、リモートワークへの移行が加速し、SaaSソリューションの採用がさらに進ん。現在、SaaS業界は数十億ドル規模の市場に成長しており、その勢いは衰えていない 。AIや機械学習といった新しい技術との融合も進んでおり、SaaSは今後も進化を続け、ビジネスのあり方を大きく変えていくと予想される
SaaSのメリット・デメリット
SaaSのメリット
- 低コスト: 初期費用、ソフトウェアライセンス費用、インフラ構築費用、メンテナンス費用などを大幅に削減できる。
- 容易な導入と展開: ソフトウェアのインストールや複雑な設定が不要で、すぐに利用を開始できる。
- 自動アップデート: ソフトウェアのアップデートやメンテナンスはプロバイダーが行うため、常に最新の機能を利用できる。
- どこからでもアクセス可能: インターネット環境があれば、場所やデバイスを問わずアクセスできるため、リモートワークにも適している。
- 高いスケーラビリティ: 利用者の増減に合わせて、柔軟に利用規模を調整できる。
- 最新のアプリケーションへのアクセス: 常に最新の機能やセキュリティアップデートが提供されるため、常に最適な状態でソフトウェアを利用できる。
- リソースの効率的な利用: マルチテナントアーキテクチャにより、サーバーなどのリソースが効率的に利用される。
- モバイルワークフォースの容易な実現: スマートフォンやタブレットなど、様々なデバイスからアクセスできるため、場所にとらわれない働き方を支援する。
- データ損失のリスク軽減: データはクラウド上に保存されるため、ローカルデバイスの故障などによるデータ損失のリスクを軽減できる。
- IT部門の負担軽減: ソフトウェアのインストール、設定、アップデート、保守管理などを自社で行う必要がないため、IT部門の負担を軽減できる。
- 幅広い採用と容易なオンボーディング: 多くのユーザーに受け入れられており、新しいユーザーの導入も比較的容易。
SaaSのデメリット
- インターネット接続が必要: 常に安定したインターネット接続環境がなければ、ソフトウェアを利用できない。
- カスタマイズの制限: 多くのSaaSアプリケーションは標準化された機能を提供しており、自社の特定のニーズに合わせて自由にカスタマイズできない場合がある。
- セキュリティとデータに関する懸念: 重要なデータをSaaSプロバイダーのサーバーに預けることになるため、セキュリティ対策やデータプライバシーに関する懸念が生じる可能性がある。
- コントロールの喪失: ソフトウェアのバージョンアップやメンテナンスのタイミングなどを自社でコントロールできない。
- アプリケーションの互換性の問題: 利用するSaaSアプリケーションによっては、自社の既存システムや他のアプリケーションとの互換性が低い場合がある。
- サービスプロバイダーへの依存: SaaSの利用はサービスプロバイダーに依存するため、プロバイダーのサービス停止や事業継続性に影響を受ける可能性がある。
- 契約上の義務とライセンス制限: SaaSの利用には契約が伴い、ライセンス数や利用規約などを遵守する必要がある。
- パフォーマンスの変動: インターネットの接続状況やプロバイダーのサーバー負荷などにより、ソフトウェアのパフォーマンスが変動する可能性がある。
- データ移行のコストと複雑さ: 将来的にSaaSプロバイダーを変更する場合、データの移行にコストや手間がかかる可能性がある。
- ベンダーロックインのリスク: 特定のSaaSプロバイダーに依存しすぎると、将来的に他のサービスへの移行が困難になる可能性がある。
- ダウンタイムと信頼性の問題: SaaSプロバイダーのシステム障害などにより、一時的にサービスが利用できなくなる可能性がある。
- 潜在的な隠れたコスト: 利用量が増加したり、追加機能を利用したりするにつれて、当初の想定よりもコストが増加する可能性がある。
SaaSの注意点
aaSを利用する際には、その利便性の裏に潜む注意点や、陥りやすい落とし穴を理解しておくことが重要。
- セキュリティ: SaaSアプリケーションはインターネット経由でアクセスするため、アクセス管理が非常に重要になる。誰が、いつ、どこからアクセスできるのかを適切に管理しなければ、機密情報が漏洩するリスクが高まる。また、SaaSアプリケーションの設定ミスもセキュリティ上の脆弱性につながる可能性がある。多くのSaaS製品は複雑な設定項目を持つため、誤った設定をしてしまうと、意図しない公開設定になったり、アクセス制限が不十分になったりする恐れがある。規制遵守も重要なポイントであり、業種によっては、データの保管場所や取り扱いに関して特定の規制が課せられている場合があるため、利用するSaaSがこれらの規制を遵守しているかを確認する必要がある。データの保存場所や保持期間についても、SaaSプロバイダーのポリシーを十分に理解しておく必要がある。万が一の災害に備えた復旧体制が整っているかどうかも確認しておきたい。そして、プライバシーやデータ侵害に関する対策も重要であり、SaaSプロバイダーがどのようなセキュリティ対策を講じているのか、データ侵害が発生した場合の対応はどうなるのかなどを確認しておく必要がある。SaaSプロバイダーはアプリケーション自体のセキュリティを確保するが、利用するユーザー側もパスワードの適切な管理や不審なアクセスへの注意など、データの保護に責任を持つ必要がある。リスクの高いアプリケーションの利用や、必要以上のアクセス権限を付与することも避けるべき。
- 契約とコンプライアンス: SaaSの利用には必ず契約が伴うため、契約内容を十分に理解することが重要。特に、データ保護に関する条項、サービスのサービスレベル契約(SLA)、ライセンス制限、契約解除条件などはしっかりと確認しておきたい。ライセンス数を超過して利用した場合のペナルティや、規制遵守に関する責任の所在についても注意が必要。
- データの管理と移行: SaaSで扱うデータの所有権は誰にあるのか、データはどこに保存されるのか、定期的なバックアップはどのように行われるのか、復旧体制はどうなっているのかなどを確認する必要がある。また、将来的にSaaSプロバイダーを変更する可能性も考慮し、データ移行のプロセスや費用についても事前に確認しておくことが望ましい。特定のプロバイダーに依存してしまうベンダーロックインのリスクも念頭に置き、データを容易にエクスポートできるかどうかを確認することも重要。
- パフォーマンスと信頼性: SaaSの利用はインターネット接続に依存するため、インターネット接続の安定性が非常に重要になる。また、SaaSプロバイダーが提供するサービスのサービスレベルや、システムの安定性も確認しておく必要がある。万が一、ダウンタイムが発生した場合の業務への影響も想定しておき、SLAで保証されている稼働時間などを確認しておくと良い
- カスタマイズと統合: SaaSアプリケーションは、多くの場合、標準化された機能を提供しており、自社のニーズに合わせたカスタマイズの自由度は低い場合がある。そのため、導入前に自社の要件とSaaSアプリケーションの機能が十分に合致しているかを慎重に評価する必要がある。また、既存のオンプレミスシステムや他のSaaSアプリケーションとの連携(統合)が難しい場合もあるため、APIの提供状況や連携方法などを事前に確認しておくことが重要。
- コスト管理: SaaSは初期費用を抑えられることが多いが、月額や年額のサブスクリプション費用が積み重なると、長期的に見ると高額になる可能性もある。また、利用量に応じて追加費用が発生する料金体系の場合、予期せぬコスト増加につながることもある。使っていないライセンスが無駄になっていないかなど、定期的に利用状況を見直し、コスト最適化を図ることが重要。従業員が個人的に契約しているSaaS(シャドーIT)も、セキュリティリスクやコスト増の原因となるため、適切な管理体制を構築する必要がある。
SaaSの業界での使われ方
SaaSは、その柔軟性、拡張性、コスト効率性から、様々な業界や分野で幅広く活用されている
- 金融サービス: 金融業界では、顧客との関係を強化するための顧客関係管理(CRM)システム、顧客がオンラインで銀行取引を行うためのオンラインバンキングプラットフォーム、リスクを評価し管理するためのリスク管理ツール、将来の財務状況を予測するための財務計画と分析ソフトウェア、不正な取引を検出するための不正検出システムなど、多岐にわたるSaaSが利用されている。この分野におけるSaaSの導入は急速に進んでおり、市場規模は2022年の540億ドルから2027年には1300億ドル以上に成長すると予測されている
- 小売・Eコマース: 小売業界やEコマース分野では、商品の在庫状況を管理するための在庫管理システム、顧客情報や購買履歴を一元管理し、パーソナライズされたサービスを提供するCRM、売上データを分析し、販売戦略の改善に役立てる販売分析ツール、店舗での販売処理を行うPOS(Point of Sale)システム、オンラインストアを構築・運営するためのEコマースプラットフォーム、メールマガジンなどを自動配信するマーケティング自動化ツールなどが活用されている。この分野のSaaS市場も大きく成長しており、2022年の481億ドルから2027年には1389億ドルに達すると予測されている
- ヘルスケア: ヘルスケア業界では、患者の医療記録を電子的に管理する電子健康記録(EHR)システム、オンラインで医師の診察を受けられる遠隔医療プラットフォーム、患者の予約をオンラインで管理する予約スケジューリングシステム、医療費の請求や支払い処理を行う請求と請求書発行ソフトウェア、患者が自身の医療情報にアクセスできる患者ポータル、医療データを分析して疾病の傾向などを把握するデータ分析ツールなどが利用されている
- テクノロジー・マーケティング・広告: テクノロジー、マーケティング、広告業界は、SaaSの採用率が特に高い分野。これらの業界では、顧客との関係構築と維持のためのCRM、マーケティング活動を自動化するマーケティング自動化ツール、チーム内のコミュニケーションや情報共有を促進するコラボレーションとコミュニケーションツール、プロジェクトの進捗管理を行うプロジェクト管理ソフトウェア、会計処理や財務管理を行う会計と財務管理ソフトウェア、従業員の採用や労務管理を行う人事管理(HRM)システム、顧客からの問い合わせに対応するための顧客サポートツール、サイバー攻撃からシステムやデータを保護するサイバーセキュリティツール、データを分析しビジネス上の意思決定を支援する分析とビジネスインテリジェンス(BI)ツールなど、あらゆる業務でSaaSが活用されている
- 製造業: 製造業においても、SaaSの導入が進んでいる。生産計画、在庫管理、購買管理、販売管理など、企業の基幹業務を統合的に管理するエンタープライズリソースプランニング(ERP)システム、サプライヤーとの連携や物流を最適化するサプライチェーン管理ソフトウェア、顧客との関係を強化するCRMなどが活用されている。
SaaSの技術的な詳細や仕組み
SaaSの技術的な詳細として、そのアーキテクチャの主要な要素を解説する。
- マルチテナントアーキテクチャ: SaaSの最も重要な特徴の一つが、マルチテナントアーキテクチャ。これは、一つのソフトウェアアプリケーションとその基盤となるインフラストラクチャ(サーバー、データベースなど)を複数の顧客(テナント)が共有する仕組み。各テナントのデータは論理的に分離され、他のテナントからアクセスできないように設計されているため、セキュリティは確保される。このアーキテクチャにより、SaaSプロバイダーはハードウェアやソフトウェアのリソースを効率的に利用でき、運用コストを削減できる。その結果、利用者は比較的低価格でサービスを利用することが可能。
- スケーラビリティ: SaaSアプリケーションは、利用者の増加やデータ量の増大に柔軟に対応できるスケーラビリティを持つように設計されている。これには、サーバーの処理能力やストレージ容量を増強する垂直スケーリングと、複数のサーバーを追加して負荷を分散する水平スケーリングの二つの方法がある。多くのSaaSプラットフォームでは、需要に応じて自動的にリソースを調整する自動スケーリング機能が実装されており、常に安定したパフォーマンスを維持できるようになっている。
- APIと統合: 多くのSaaSアプリケーションは、他のソフトウェアやサービスと連携するためのAPI(Application Programming Interface)を提供している。APIを利用することで、異なるアプリケーション間でデータを交換したり、ワークフローを自動化したりすることが可能。これにより、SaaSアプリケーション単体では実現できなかった機能を追加したり、既存のシステムと連携させてより高度な活用が可能。
- さまざまなSaaSアーキテクチャ: SaaSのアーキテクチャには、マルチテナントの他に、シングルテナントアーキテクチャやハイブリッドアーキテクチャなどがある。シングルテナントアーキテクチャは、一つの顧客に対して専用のソフトウェアインスタンスとインフラを提供するもので、より高いカスタマイズ性やセキュリティを求める場合に選択されることが多いが、コストは高くなる傾向がある。ハイブリッドアーキテクチャは、シングルテナントとマルチテナントの要素を組み合わせたもので、特定のニーズに合わせて柔軟な構成が可能。
SaaSまとめ
- SaaSはクラウド経由で利用するソフトウェア: インストールや管理の手間がなく、インターネットがあればどこでも利用可能です。
- コスト効率とスケーラビリティが魅力: 初期費用を抑えられ、ビジネスの成長に合わせて柔軟に利用規模を調整できます。
- 多様な分野で活用される重要なモデル: 日常的なサービスから企業の基幹システムまで、幅広い用途で利用されています。

SaaSについて理解は深まりましたか?もしこの記事が少しでもお役に立てたなら、ぜひコメントで感想や疑問点を教えてください。あなたの声が、今後の記事作成のヒントになります。

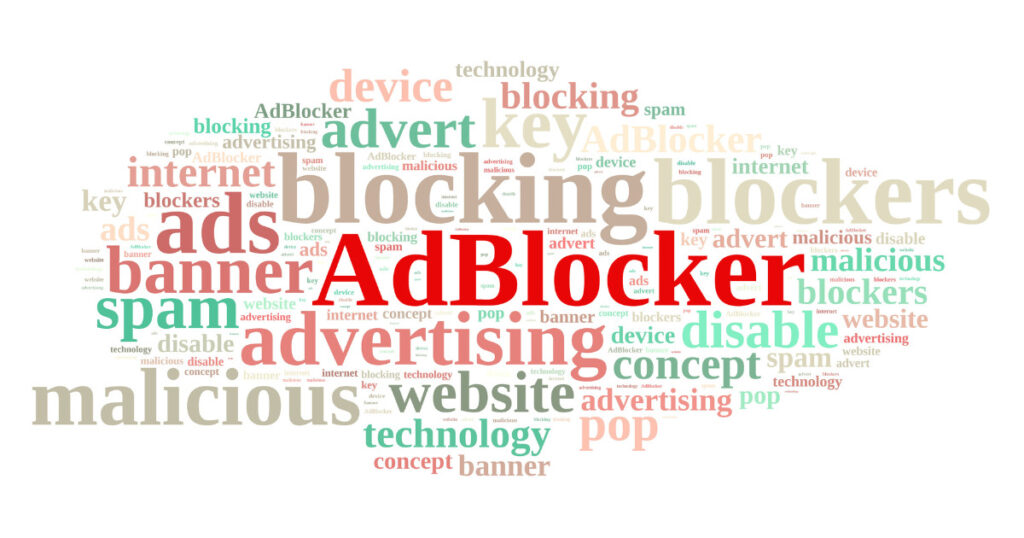

コメント